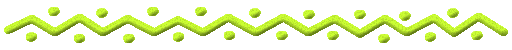
散 文 抄
| ①(文章) ②(萩原先生を哭す) ③(読み方) ④(水晶の観音) | |
| ①文章 ([三人」昭和16年6月) | 富士君が文章を書けといふ。いまのところわたしの文章を需めるのは、富士君ぐらゐのものである。 僕ら詩人には文章は苦手なところがある。稀に書いても、読む人の方では苦笑してゐるだけのことが多い。僕らに苦手なわけは何故かといふと、僕ら詩人が平素詩で表現しようとするーといふより表情しようとするーものには題材といふものはない。 譬へて言へば、天地間の風や水の、漾揺とでもいへる風のものである。 南無阿弥陀仏とか南無妙法連華経といへばもそれで充分なものである。 また、ああ、とか、花、とか言へばそれですむものなのだ。 表現と言へば、そんな時、僕らにはてにをはだけが大切。 題材もなくてにをはだけで、どうして文章が苦もなくつづれよう。 ましてや、通俗の達意と流暢とを欲しがる読者に気に入る筈がない。 又詩人は、他を顧みて物を言ふ現代の悪癖に染つてゐない点もあるのである。 世間の人の面白がる文章といふものには、必ずこの悪癖が一杯してゐなければならぬ。 又詩人には教師風の懇切鄭寧さもない。他人に対して面倒くさがりである。 天のみぞ知るといつた鷹揚さもある。 詩の書けない時は、文章などより、琴でも弾いてゐたいものと思ふ。 富士君でいふと絵であらう。口の中でもぐもぐとわけのわからぬことを呟き、絃をいいかげんにごそごそ掻いてをれば、風の音や松の音の方で勝手に遠くから微妙音で来り和すだらう。琴は小さい、膝にのる位の、但し古風の、枯れ切つた木材のものがよろしい。そんなものがあるかどうかは知らない。 昔の琴後集といふ本の題はいいものだ。僕のこれからの詩集もそんなものでありたい。 富士君と二人会ふと、いつも隠棲の話が出る。しかし富士君の方はどうか知らんが、わたしは、熱望にかかはらず、結局それは出来さうにない。 わたしはむしろ、陋巷趣味である。金魚と朝顔の鉢と二階借りに琴といつた趣味である。 富士君だつてせいぜい、旅の絵師になつて、田舎の宿屋で宿銭の代わりに、尺物何か塗りたくつて、こそこそと次の宿屋へと急ぐ式の余生であらう。 怪奇な、どこか夫子自身に似たところのある君の童子の絵は、生半可な風流人がたまたま泊まり合はせて眺め、妙にほめたてて宿屋の主人をびつくりさせ、宝物あつかひにさせたりなどする珍話が出るかもしれぬ。 あの絵にはそんなおそれが充分にある。 芸術といふものは誠さへこもつてをれば、下手なほどよろしい。 (散文抄のはじめに戻る→) |
| ②萩原先生を哭す (全文) (「四季」昭和17年9月 萩原朔太郎追悼号) | 先生が長く御不快の由承つたのは今年の一月頃であつた。用事の序に「四季」の編集部から知らせて貰つた。それ以前既にかなり永い間お引籠り中であるらしかつた。こんなに遠隔の地にゐて誰もが知つゐることを何も知らずに過ごすのを情けなく思つた。
三月の休暇になるとすぐ上京してお見舞に伺つた。二年以上も御機嫌伺ひのお手紙も差上げることもなくすごしてゐたお詫びの心持もこめて、何だか平服では行けない気がして、滅多に著ることもない紋付、袴を用意して行った。二日ほどつづけて参上したが、お会ひ出来なかつた。
先生には通じてゐないじゃないかと思はれる節もあつたが、仕方なかつた。お葬式に宇治からはせつけた小高根二郎君の通信によると、その後で取次に出られた人はひどく先生に叱られたとのことであつた。
私はその文書をよみながら、胸のずーんとする痛切な思ひにうたれ、先生はほんとうに亡くなられたのだといふことを実感したのであつた。それにしても私は油断してゐるところもあつた。四五年前、先生が大阪においでの折、先生の思ひつきで天王寺公園のラジュウム温泉といふ大きな風呂に一緒には入りに行つたことがあつた。
先生は幼時ここで万国大博覧会のあつた時見物においでになつて、通天閣やケーブルカーをなつかしく印象してゐらつしやるやうであつた。しかしその時は一向興趣を覚えられない風で、まひるの白々しい大風呂の中を見まはしながら、つまらないつまらないと云つておいでになつた。私はその時、先生の御体格の中々立派でおありのことに驚きもし力強くも思つたのであつた。そのことがいつも頭にあつた。取次の方に強ひておねがひしなかつたのは油断であつたとくやまれる。数ならぬ弟子の私にさへ、この十年間先生の賜つた御懇情のほどは、有難い極みであつた。私は文学と師弟の道を同時に先生によつて知らされた無上の幸運を切に思ふ。
このことは、私の最も親しい数人の友人は同情してくれることと思ふ。この十年間こそは、自分の無味偏窟と思はれる生涯で意義ある唯一の時期であらう。これから先の歳月をおそれる気持ちをどうしようもない。それにしてもわたくしは、先生にとつて何といふ面白味のない弟子であつたことであろう。
この十年間は先生の御一生の中でも最も、若い詩人らとの交渉を忌み嫌はれることのすくなかつた時期とおききしてゐる。にも拘らず、拝趨の機をわたくしは五回以上つくつてゐない。 季節のお見舞いさへ何度差上げたことやら、只友人らが先生の文学の意義や御日常を、尊敬と思慕とを以て語る言葉や文章を、この上なくうれしと思つてゐたのであつた。わたしはお葬式にさへ出られなかつた。
三月以来自分の健康は、いよいよどんづまりに来たのではないかと思はれるほど悪かつた。お葬式の模様を知らせて貰ひ、それに参列出来た友人に強い嫉妬を感じた。南方に行つて留守の田中克己君さへ自分よりはましだと思つた。まことにうすい現世の縁であつたと思ふ。 (散文抄のはじめに戻る→) |
| ③読み方(全文) (「大阪毎日新聞」 昭和18年9月) | 読書といふものは、丁寧に深切でありたいものだ。 一字一字を指で押へて、丁度著者が書いてゆくのと同じくらゐの速度で読みたいと、理想的にはさう願つてゐる、お互いに大多忙の時である,しかし読書の時間を見出した時の心構は、そんなにありたい。 わが国の文学の道は、言霊の風雅といふことにある。それは、文字の隠微なところに宿るのだ。 まあ大凡の要旨はかうであるとか、かうだからかうなるといつた風の性急で粗雑な読み方では感得出来ないだろう。 発想法のことは一番根本的で肝腎なことだが、短文であるからここではいはない。 もう少し軽いことでいふなら、助詞や助動詞のやうな、それだけでは意味のない言葉こそが、名詞や動詞のやうに誰にも明瞭である言葉より大切だ、といつてもいいのだろう。その大切さは、深切な読み方でだけわかる。 そのへんのことを腹にしみて悟るために、自分は古来の和歌を毎日二、三首づつ読むことを、忙しい日の読書法としてゐる。 古典を読むといふことが、広く行はれてゐるさうだが、そこから知識を得てくることよりも、むしろわが国の本当の読書法を悟ることの方を、期待してゐる。 正しい読み方で、不知不識の間に養はれる志の方に期待してゐる、そして、日本の文学のことを敷島の道と呼ぶ呼び方を真に納得する時、さもさも忙しげに、現代の氾濫する本を読みあさる悪癖から救はるればよいと願ふのである。 (散文抄のはじめに戻る→) |
| ④水晶の観音(全文) (「舞踏」昭和26年2月号)  水晶の観音入口 左の碑に水晶観音と刻まれている | 私の生れた町から、三、四里、有明海に沿つて行つたところに、Yといふ小さい部落があつて、そこから谷川沿ひに多良岳をわけ入つた山の奥に、小さい朽ちたお堂がある。 その傍の滝が見事なので、そのお堂は有名である。(水晶の観音)といふ本尊が、小さい水晶の観音像であるさうだ。 小学校のころ遠足にいつたやうな気がする。本当に行つた事があるのかどうか、はつきりしないが、脳裏にあざやかな幻のやうに浮ぶ。 去年、病気のひどかつた頃、故郷の姉(もう五十五歳)から手紙がきて、病の苦しいときは、「なむ・だいじ・だいひの・かんぜおんぼさつ」を唱へなさいと言つてきた。 その(水晶の観音)の堂守の尼さんは、姉の古い友人で、朝夕私のために、観音経を唱へてゐるのださうだ。 私は別に信仰の心はない。しかし、老いた姉を思ひ、しづかなしづかな深い山中の滝の傍にまします小さい観音像を思へば、ひとりでに「なむ・だいじ・だいひの・かんぜおんぼさつ」と、ひとりでに唱へられる。 (散文抄のはじめに戻る→) |
![]()